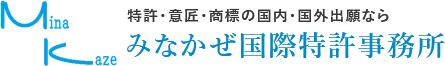特許申請(出願)を自分でする際のポイントと注意点|特許の取り方ガイド
特許申請(出願)を自分でする際のポイントと注意点|特許の取り方ガイド
こんなお悩みはありませんか?
「自分で特許を出願できるのだろうか?」 「特許庁への手続きに必要な書類や方法が分からない」 「費用や手数料をなるべく抑えて特許権を取得したい」
特許の取り方を調べてみると、明細書の作成や特許請求の範囲の書き方・構成の仕方など専門的な内容が多く、不安に感じる方は少なくありません。
もし内容が不十分な(記載要件を満たさない)書類を提出したり、新規性・進歩性を満たさない発明を出願してしまうと、拒絶理由通知を受け、拒絶対応が必要になり、時間も費用も余計にかかることになります。
最悪の場合、権利が取れないか十分な権利保護ができずに、自社製品が侵害されるリスクもあります。
この記事では、「特許の取り方を自分で進めたい人」に向けて、流れや注意点、特許事務所に依頼した場合との違いを分かりやすく紹介します。
目次
特許取得のメリットとデメリット
特許の取り方(自分で出願する流れ)
出願の際に注意したい点
特許事務所に依頼した方がよい理由
まとめ:一人で悩まず、まずは相談を
1. 特許取得のメリットとデメリット
1-1. 特許を取得するメリット
独占的権利(特許権)を得られる
他人が同じ発明の実施(製品の製造や販売等)を禁止できる。
ビジネス上の信頼性向上
取引先や投資家に対して「技術的優位性」をアピール可能。
ライセンス収入の可能性
ライセンス契約により、ロイヤリティ収入を得られる。
開発費用の回収につながる
上記等により、研究開発に投じた費用を回収しやすくなる。
1-2. デメリットやリスク
費用がかかる
出願料・審査請求料・登録料などの手数料が発生する。
時間がかかる場合がある
特許庁の審査期間が数年程度になる場合もある。
拒絶のリスク
新規性や進歩性を満たさない等で、特許出願が拒絶されると費用と時間とが無駄になる。
範囲が狭いと効果が薄い
特許請求の範囲の書き方を誤ると、権利が限定的になってしまい、権利化の十分な効果が得られない(費用と時間との無駄にもつながる)。
2. 特許の取り方(自分で出願する流れ)
2-1. 事前調査
まずは特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)などで公開済みの発明を検索し、自分の発明が新規性を満たしているか調査しましょう。
調査不足だと新規性を満たさないなどの理由で拒絶される可能性が高まります。
2-2. 書類作成
特許出願に必要な書類は以下です。
願書 明細書(発明の内容を詳しく記載) 特許請求の範囲(「請求項」という単位で記載して請求項毎に権利範囲を規定) 図面(法律上の必要書類ではないが、一般的には出願書類として添付します) 要約書
この「明細書」と「請求項」の書き方・構成が最重要ポイントです。
2-3. 出願と提出
書類を作成したら、特許庁にオンライン提出(電子出願ソフトを利用)または書面で提出します。
出願時に出願料が必要です。
2-4. 審査請求
出願後、30か月以内に審査請求を行う必要があります。
この手続きを忘れると、自動的に取り下げ扱いとなるため注意が必要です。
(なお費用はかかりますが、徒過した場合の2か月以内の回復措置はあります)
2-5. 審査と通知
特許庁の審査官が記載要件、新規性・進歩性等を審査。 問題があれば拒絶理由通知が届き、補正や意見書の提出で対応(拒絶対応)することが可能。
2-6. 登録と公開
査定により特許が認められると設定登録料を納付。 登録後、特許権が発生し、登録時の発明の内容が公開されます。
(出願から1年半の時点で登録されていない時も出願時の発明内容が公開されます)
3. 申請の際に注意したい点
3-1. 明細書・請求範囲の書き方
権利範囲が広すぎると拒絶されやすい。 狭すぎると他社が少し変更して模倣可能になる。 「自分の発明をどこまで守るのか」を意識して作成することが重要です。
3-2. 時間と費用の見積もり
出願から登録まで数年かかるケースも多い。 出願料・審査請求料・登録料・年金(登録後の1年毎の登録料)など、合計すると数十万円以上かかる場合がある。
3-3. 制度の違い
特許:高度な技術(発明)を保護(20年)。 実用新案:比較的簡易な技術(考案)を無審査かつ短期間の間保護(10年)。 意匠:デザインを保護。
自分のアイデアがどの制度に当てはまるか確認することが大切です。
4. 弁理士や特許事務所に依頼した方がよい理由
4-1. プロに依頼するメリット
専門的な書類作成が可能
明細書や請求項の適切な書き方を熟知している。
特に、権利範囲を、どこまで、かつ、どの様な構成で記載するか、または、拒絶理由通知が来た場合の補正を考慮した明細書や請求項の書き方等。左記は記載要件を満足しつつ記載することになる。
拒絶理由への対応がスムーズ
補正・意見書の作成、特許庁とのやり取りを代行。
単に代行するだけではなく、適切な補正や意見書の内容で対応します。
調査力が高い
類似特許や技術の範囲を正確に把握できる。
類似技術の範疇で、「進歩性」をも満足するかも調査できる。
4-2. 自分で申請する場合との比較
項目
自分で出願
弁理士に依頼
費用
安い(手数料のみ)
高い(依頼料+費用)
時間
自分で調査・作成に多くかかる
専門家が効率的に進める
成功率
権利化できないか十分権利保護できない可能性が高い
特許取得率が高い
メリット
費用を抑えられる
確実性・安心感が高い
4-3. 依頼先を選ぶポイント
特許事務所の実績や対応分野を確認。 どこまで親身に対応してもらえるか。 無料相談を利用して、相性や説明の分かりやすさを確認。
5. まとめ:一人で悩まず、まずは相談を
特許の取り方には、調査 → 書類作成 → 出願 → 審査請求 (→ 拒絶対応 )→ 登録という流れがあり、自分で進めることも可能です。
(拒絶対応は、拒絶理由通知を受けた場合のみの対応となります)
しかし、明細書の作成や特許請求の範囲の書き方を誤ると、拒絶理由通知や侵害リスクにつながり、結果的に時間も費用も余計にかかることがあります。
「自分で申請したいけれど不安がある」「発明の権利化を確実に進めたい」――そんな方は、まず特許事務所への相談をおすすめします。
当事務所(みなかぜ国際特許事務所)では、
分かりやすい説明
· 各技術分野に精通し、かつ、適切な明細書・請求項作成が可能
(特に所長は慶應義塾大学理工学部卒業後、メーカーで研究開発20年勤務の経験を有して各技術分野に精通しており、親身に特に発明者の立場で製品に則して、請求項を設定構成したり、補正を考慮した明細書や請求項を記載すること、ご説明をすること、が可能です)
調査前のご相談は無料
といった強みを活かし、特許出願から登録まで安心してお任せいただけます。